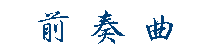 (1) 「講義室、変更になってますよ。一緒に行きましょう」 「いつもありがとう、クオータ」 微笑んで、オラクルは言った。最初にクオータが話し掛けて来たのは、入学してすぐの頃だった。 ――何かお手伝いしましょうか? クオータがそう言ったのは、無論、オラクルの白い杖__盲人である事を示す__を見たからだ。話し掛けたのは別の理由からだが、その事に、オラクルは気づかなかった。 ――ありがとう。でも、大丈夫だから… この大学に進学が決まった時、オラクルは兄のコードに付き添ってもらい、自分が行くべき講義室の場所を覚えた。点字での受験に対応しているとはいえ、盲学校に比べれば、不便な点が沢山ある。それでも、出来るだけの事はしたかった。自分が、無力だとは思いたく無い。 「窓際の席にしましょうか?」 言って、クオータは軽く、オラクルの腕を掴み、最前列の椅子に座らせた。オラクルは講義を録音する必要があるので、いつも最前列に座る。そして、大概はクオータがその隣に席を占めていた。 講義室の変更や休講、その他の様々な情報は、殆どの場合、普通の紙に書いて貼り出されるだけだ。それを、オラクルは読む事が出来ない。クオータのように、いつも同じ講義をとる誰かが教えてくれるので無ければ、途方に暮れていた事だろう。 「今度、家に遊びにいらっしゃいませんか?週末にでも」 入学して半年ほど経った頃、そう、クオータは言った。 「誘ってくれたのは嬉しいけど、今週末には予定があるから」 「…本当に?」 「__え…?」 そう、オラクルは聞き返した。 「本当に、嬉しいと思ってくれたのですか?社交辞令では無く?」 一瞬、オラクルは返答に窮した。クオータはいつも親切にしてくれる。その事に感謝はしている。が、何故、彼がそうするのか、疑問に思わないでも無かった。 「…構いませんよ、無理に答えなくても」 オラクルの心を見透かしたかの様に、クオータは言った。 「あなたに想われているのは、どんな人なんでしょうね…」 クオータの言葉に、オラクルの脳裏に蘇ったのはオラトリオのイメージだった。オラクルは自分で、それを意外に思った。 「…何の話をしてるんだ?」 「週末に、予定があると言ったじゃありませんか。恋人と過ごすのでしょう?」 オラクルは何度かまばたいた。クオータの言葉は予想外だったから。 「そんな事は言っていないよ。家族だけで、お茶会をするんだ」 「いつか、お兄さんが来てましたよね。余り、あなたとは似てない様ですけど」 オラクルは口を噤んだ。クオータはいつも穏やかに話す。言葉づかいも丁寧だ。だが、そうであるにも拘わらず、或いは、そうであるからこそ、柔らかい言葉の内に、鋭い刺を含んでいる様に、感じずにはいられない。 「どうかしたのか?」 オラクルを迎えに来たコードは、車の助手席に座る相手にそう、聞いた。 「どうかって…?どうかしたように見える?」 「ああ。何かを気にかけ、悩んでいるように見える」 相変わらず、ぶっきらぼうと言える口調で、コードは言った。世を拗ね、世を見下した様な態度。澄んだ琥珀色の瞳は、常に相手を斜めに眇める。 だがそれは、一つの仮面なのだ。仮面の下には別の顔が在る。それを知る者は、僅かしかいないけれども。 「…クオータって人の事なんだけど…」 「あの男か。お前につきまとっている」 オラクルは、意外そうな表情を浮かべた。 「…知ってるの?」 「お前につきまとっている事は知っとる。迷惑なら、はっきりそう言えば良い」 コードの言葉に、オラクルは俯いた。クオータには、いつも親切にして貰っている。そう、邪険には出来ない。 「迷惑とか、そういうんじゃ無いけど…何て言って良いか、判らない…」 「親切そうに思えるのはただの下心の現れだ。あんな男に、気を許すな」 「オラクル」 数日後、講義が終わり、帰ろうとした時に、オラクルは聞きなれた声で呼びかけられた。 「オラトリオ…」 「この近くに用があったんで、寄ったんだ。元気か?」 耳に心地良い声。明るい口調。言葉づかいは丁寧な方では無いが、いかにも彼らしい。オラクルは微笑んだ。オラトリオが、怒っているのでは無いのが嬉しかった。 ――私だって、一人で買い物にも行けるし、料理だって作れる。 ――判ってるぜ、んな事ぁ。 ――だったら…構わないでくれ… あんな事を言うべきでは無かった。あんな言い方をすべきでは無かった。ただ、オラトリオの負担になりたく無かった。それだけなのだ。 「今日、家に飯を食いに来ないか?」 「…そうだね、行っても良いなら」 「来ても良いどころじゃねえぜ。シグナルとちびが喜ぶだろう。パルスや姉さんも、な」 一番、それを嬉しく思うのが誰なのか、オラトリオは口にしなかった。 「じゃ、行こうぜ。途中、どっかに寄る用事があんなら付き合うから、そう言えよ」 従兄弟の手を取って、オラトリオは言った。オラクルの隣の席に座っていた片眼鏡の青年の事は無視した。彼が、じっとこちらの方を見ている事に、気づいてはいたけれど。 その日も、朝からだるかった。日ごとに気温の下がるこの季節はいつも、そうだ。尤も、夏の暑さにも弱いし、秋は悪夢に悩まされる事が多い。冬ばかりが、厭な季節という訳でも無い。コードやオラトリオからは無理をしすぎると言われるけれど、いつも休んでばかりはいられない。 「大丈夫ですか?何だか、顔色が良くありませんよ」 「__ああ…」 クオータに、声をかけられた。何だか、答えるのも億劫だ。 いつも通りに講義を録音する。が、全く耳に入っていなかった。熱っぽく、悪感がする。今日は、早く帰った方が良さそうだと、オラクルは思った。講義が終わり、席を立ったとき、足元がふらついた。それを、クオータに支えられた。 「大丈夫ですか?__いえ、大丈夫な筈がありませんね。真っ青ですよ。送って行きますから、一緒に帰りましょう」 「…お前はまだ、講義があるのだろう」 「そんな事は、構いません。それより、歩けますか?」 独りで帰れると、オラクルは言おうとした。誰かの世話にばかりなるのは厭だ。だが、この時には逆らわなかった。そんな気力も無かったのだ。頭がぼうっとしている。暑いのに、寒くて仕方が無い。頭痛と、悪寒と、吐き気と…。 気がつくと、ベッドに寝かされていた。誰かが、額の上のタオルを取り替えてくれる。 「気がついた様ですね」 クオータの声だ。ではここは、クオータの家なのだろう。 「…私は…」 「倒れたんですよ。それで、私の家に連れてきました」 「ごめん、迷惑かけて…」 溜息とともに、オラクルは言った。 誰かの世話になり、周囲に特別に気遣われる自分が厭で、一人暮らしを始めた。不便さには慣れたけれど、悪夢に苛まされる頻度が増えた。悪夢を”見た”翌日には余り、食欲もわかない。増してや、中身が何なのか判らないレトルトなど、食べる気にもならない。 元々、丈夫な身体ではないのに、そんな事をしていればどうなるか、自分でも、判っていた筈だ。 「少しも迷惑なんかじゃありませんよ。私は一人暮らしですから。泊まって行って貰っても構いません」 「そうはいかないよ。もう少しだけ、休ませて貰ったら、帰るから…」 「でも、もう夜ですよ。ご家族に連絡しましょうか?」 クオータの言葉に、自分も一人暮らしなのだとオラクルは言った。 「だったら…帰す訳にはいきませんね。体調が回復するまでは、独りにしておけません」 「大丈夫だよ、私は」 僅かに眉を顰め、オラクルは言った。意地を張っているのだと、自分でも判っている。人の手を借りた方が楽なのも。それでも、嫌、それだからこそ、頼りたくは無いのだ。 クオータは黙ったまま、オラクルを見つめた。オラクルが意識を回復するまで、ずっと、傍らで見つめていたのだ。初めて講義室で見かけた時から、ずっと、彼は、オラクルを見つめ続けていた。片方だけの、碧い瞳で。 「オラトリオ…でしたね」 不意にクオータがオラトリオの名を口にしたので、オラクルは意外に思った。 「彼が…あなたの想い人なのですか」 「従兄弟だよ、オラトリオは」 「それだけでは、否定にはなりませんね。お兄さんで無ければ、コードがあなたの恋人だと思ったところですけれどね」 オラクルは、クオータが何を言おうとしているのか判らなかった。幾分、不安になる。 「…何が言いたいんだ…?」 「聞いているのですよ。あなたの恋人が、誰なのか」 「__いないよ、そんな人…」 そんな事を聞かれる謂れも、答える理由も無いと思いながら、オラクルは言った。不安が募る。僅かな口調の変化から、クオータが、強い感情を持っているのが感じられる。 「私では、いけませんか」 「__え…?」 「初めて見かけた時から、ずっとあなたの事を想っていました。もう、ずっと以前から、あなたの様な人に出会える時を、待っていたのです…」 言って、クオータはオラクルの頬に触れた。オラクルは驚き、クオータの手を振り払った。ベッドに上半身を起こすと、目眩を感じた。 「まだ、起きてはいけませんよ」 言って、クオータはオラクルの華奢な両肩に手を置いた。オラクルはそれを振り払おうとした。が、クオータは手を離さない。 「…放せ」 「そんなに、驚かないで下さい__可愛い人ですね、あなたは」 「放せと言ってるんだ。私は帰る」 「落ち着いて下さい。何も、取って食おうとしてるのではありませんよ」 軽く笑って、クオータは言った。オラクルは、口を噤んだ。 半年の間、殆ど毎日、隣の席で講義を受けているが、未だにクオータには親しみを感じられない。穏やかさの下に冷たさを、丁寧さの内に残酷さを隠している様で… |